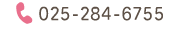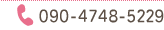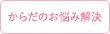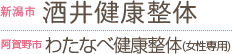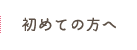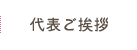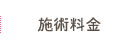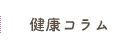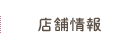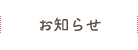カテゴリ
月別 アーカイブ
- 2025年5月 (1)
- 2024年8月 (2)
- 2024年7月 (4)
- 2024年6月 (3)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (3)
- 2023年9月 (2)
- 2023年8月 (7)
- 2023年2月 (1)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (2)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (3)
- 2022年5月 (2)
- 2022年4月 (1)
- 2022年2月 (1)
- 2021年12月 (1)
- 2021年10月 (2)
- 2021年7月 (1)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (2)
- 2021年1月 (1)
- 2020年12月 (3)
- 2020年11月 (3)
- 2020年10月 (7)
- 2020年9月 (1)
- 2020年5月 (5)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (6)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (2)
- 2019年12月 (4)
- 2019年11月 (4)
- 2019年10月 (4)
- 2019年8月 (1)
- 2019年5月 (1)
- 2019年4月 (1)
- 2018年8月 (1)
- 2018年4月 (2)
- 2018年3月 (2)
- 2018年2月 (1)
- 2018年1月 (3)
- 2017年12月 (9)
- 2017年11月 (12)
- 2017年10月 (10)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (2)
- 2017年7月 (16)
- 2017年6月 (1)
- 2015年10月 (5)
最近のエントリー
HOME > 健康コラム > アーカイブ > 健康と美容 > 2ページ目
健康コラム 健康と美容 2ページ目
横になってゆっくり
 睡眠が人の健康に影響するのは、ご存知だと思います。
睡眠が人の健康に影響するのは、ご存知だと思います。疲労回復をはじめ、記憶の整理など日常で使った脳内の整理も行います。
最近では、睡眠時間が少ないと認知症やうつ病の原因にもなる他、 心血管の病気や動脈硬化にもなりやすいとも言われています。
それだけ、睡眠は人の疲労を回復させる以外に、 脳内の整理にも重要な働きがあるようです。
しかし、睡眠不足や不規則な睡眠になると 体の回復力が低下し、特にアテローム性動脈硬化になりやすいとも言われます。
横になって寝た状態は心臓への負担が少なくなるので、眠れなくても横向きにで寝るのは心臓や血管には良い効果があります。
体のリフレッシュのためにも、寝るだけでなく、横になってゆっくりするのも必要かもしれませんね。
2024年5月14日 16:58
DASH食
 血圧を低下させ、心血管疾患の予防にも推奨されているDASH食。
血圧を低下させ、心血管疾患の予防にも推奨されているDASH食。これは野菜や全粒穀類、ナッツ・豆類、果物、低脂肪乳製品を多く摂取し、塩分、砂糖などで甘くした飲料、赤身や加工肉の摂取を抑えた食事法です。
増やす栄養素としては、主にカリウム、カルシウム、マグネシウム、食物繊維、タンパク質となっています。
この食事が、「塩分を排出させる食事」としても再注目されているようです。
塩分の排泄を促すカリウムや食物繊維、血圧調整を担うカルシウム、血圧上昇の抑制に影響するマグネシウムなどが豊富に含まれている食材を多く取ることで、 塩分排出と血圧を下げることができるのです。
このような食事と共に、生活習慣病に効果的と言われる地中海食(オリーブオイルや魚介類を多く含む食事など)も合わせると、飽きることなく食事ができそうです。
健康法はたくさんありますが、運動や食事も長期間続けられるものが効果が出やすいかもしれませんね。
2024年5月 5日 17:08
脳への刺激にきのこ?
 認知機能に影響するものとして、脳への刺激は大切です。
認知機能に影響するものとして、脳への刺激は大切です。これによって脳内の血流が増え、酸素や栄養が行き渡るからです。
また、ビタミンやミネラルなどのサプリメント、キノコ類を食べても認知機能の低下を防ぐ効果がある場合もあり、抗炎症作用が関係しているとも考えられています。
反対に塩分の取り過ぎは血管などに炎症が起きやすく、結果的には認知機能の低下につながる可能性も出ています。
血管なので体内での炎症は分かりにくい所がありますが、毛細血管のダメージも多くある可能性から脳内の血管が傷つきやすく、認知機能をはじめ、様々な機能が低下することが考えられます。
日頃の食事も大切ですが、自分自身が楽しく興味を引かれるような、新しい刺激も脳には必要ですね。
2024年4月24日 09:43
血糖値を上げにくく
 糖尿病などで血糖値を上げにくい食材として、納豆や海藻類があります。
糖尿病などで血糖値を上げにくい食材として、納豆や海藻類があります。飲みのもとしては緑茶が効果があるとも言われています。
今回、ハーブやスパイスなどが糖尿病に与える影響を調査した結果、 空腹時の血糖値やヘモグロビンA1c、インスリン値の低下と関連しているようです。
ヘモグロビンA1cは、全身の細胞に酸素を送る働きがあります。
血糖値が高い状態が続くと、ヘモグロビンに結合するブドウ糖の量が多くなるので、ヘモグロビンA1cは高くなります。
この検査は過去1~2ヶ月前の血糖値を反映しますので、当日の食事や運動など、短期間の血糖値の影響を受けないのも特徴です。
なので、検査が近いからといって、食事を調整したり運動しても バレてしまうのです。
日頃から食生活が大切ですので、食材にも気をつけましょう。
今回の調査では、とくに生姜を摂取すると改善しているようです。
生姜は血流をよくする食べ物でもあるので、日本では馴染み深いものがあります。
他にもブラッククミンはヘモグロビンA1cを低下させ、シナモンもインスリンを低下させる効果があるようです。
摂取する量にもよるとは思いますが、日頃から食事に取り入れると良いかもしれません。
しかし、運動や食事量は意識するとより効果的だと思います。
2024年4月17日 09:57
老化予防にはコーヒー?
 コーヒーに関係する論文は多くあります。
コーヒーに関係する論文は多くあります。今回は、コーヒーに含まれる成分のトリゴネリンが、老化で起きるサルコペニア(筋肉減少や筋力低下など)の治療に効果がある可能性がわかってきました。
サルコペニアが起きる原因は様々ですが、その中でも、
・ミトコンドリアが新しく作られる数が減る。
・生物に必要不可欠なエネルギーのATPの生成が減る。
などが、筋肉老化の特徴に関係していることが明らかになっています。
コーヒーなどの植物に存在していて、人の体内でもビタミンB3から少し作られるトリゴネリンという物質が、サルコペニアになっている高齢者の血中には少ないことが多いようです。
さらに調べると、コーヒーを1日3杯以上飲む人は、1日1杯未満の人に比べて、サルコペニアの有病率が60%ほど低いという調査結果も出ています。
コーヒーを飲むことで今後どのくらい予防できるかはまだ未知数ですが、運動だけでなく、このような飲み物でも効果があるのは、コーヒー好きからしたらありがたいです。
2024年4月 3日 10:08
脳の萎縮予防には和食がいいかも
 おかずと汁と漬物でご飯を食べる「一汁三菜」が基本的な組み合わせといわれる和食。
おかずと汁と漬物でご飯を食べる「一汁三菜」が基本的な組み合わせといわれる和食。これは、主食であるご飯をおいしく食べるために工夫された様式だそうです。
伝統的な日本食を食べている女性は、西洋食よりも脳などにある灰白質(神経細胞の体の部分が集まっている所)の 萎縮が少ないことが、研究調査で判明しました。
ところが、男性はこのような食事をしても、脳の萎縮との関連がなかったそうです。
料理も大切ですが、使う食材も重要です。
全粒穀物や魚介類、野菜、キノコ類、大豆製品、緑茶などの摂取量が多い、健康的な食事パターンを多くするのも良いかもしれません。
しかし、今回の研究結果では女性には有効的でも、意外と男性ではそうでもないということです。
日本食は健康的ではあるものの、男女で違いが出るのは、何が関係しているのか不思議に思います。
これからの更なる研究に期待が出てきますね。
2024年3月25日 10:38
卵は体に良い?悪い?
 卵の摂取が、脂肪性肝疾患と高血圧症に対する保護的な効果を示し、週3個以上の摂取でそれらの発症リスクがより低くなる 卵について体に良い、悪いと議論されることがありますが、卵にはタンパク質だけでなく、ミネラルやビタミンなどの豊富な栄養素が含まれています。
卵の摂取が、脂肪性肝疾患と高血圧症に対する保護的な効果を示し、週3個以上の摂取でそれらの発症リスクがより低くなる 卵について体に良い、悪いと議論されることがありますが、卵にはタンパク質だけでなく、ミネラルやビタミンなどの豊富な栄養素が含まれています。食物繊維とビタミンC以外の栄養素を全て含んでおり、その栄養価の高さから「完全栄養食品」ともいわれています。
それだけ健康的な食品と思うのですが、悪く言われるのは、コレステロール量です。
日本人の食事摂取基準によると、コレステロールの摂取量は、1日200mg未満に留めることが望ましいとなっています。
卵黄1個当たりでは、180~225mgとなることを考えると、生活習慣病の「悪者」扱いされることが多いのです。
しかし、卵についていえば、卵の摂取と病気の関係性については調査した研究は乏しく、その結果には一貫性がないことが多かったそうです。
そこで詳しく調べたところ、1日当たりおよび1週間当たりの卵の摂取量は、脂肪性肝疾患や高血圧が無いの人の方が多かったとの結果が出ています。
食生活も様々ですが、卵のように栄養価が高いとコレステロールの吸収に違いがある可能性もあります。
やはりバランスが取れた食事が、一番健康的ですね。
2024年3月21日 10:47
ブロッコリー
 人気な野菜の一つに、ブロッコリーがあります。
人気な野菜の一つに、ブロッコリーがあります。ブロッコリーは農林水産省から50年ぶりに新しく指定野菜とされ、注目もされています。
指定野菜とは、国が消費量が多い野菜をリストアップしたもので、それだけ消費量も多いのでしょう。
個人的には、ダイエットの時に出てくる野菜のイメージがありますが、ブロッコリーは、ダイエットに役立つだけでなく、体にも良い効果があるようです。
アメリカのサウスフロリダ大学の研究では、全身の慢性炎症と死亡率の低下に関連していたことが分かってきました。
脂肪を蓄えている細胞(脂肪細胞)が分解される時には、炎症が体内で生じます。
この炎症は自然と収束しますが、肥満などの場合、脂肪を溜めこみすぎているので、収束することができなくなります。
これが、慢性炎症という状態です。
これが続くと、生活習慣病のリスクが高くなっていきます。
ブロッコリーを摂取することで、どれだけ炎症が落ち着かせるかは不明なところもありますが、ダイエットをしながら摂取すれば、相乗効果は期待できそうです。
2024年3月12日 12:16
認知症
 認知症になるリスク因子は、いろいろとあります。
認知症になるリスク因子は、いろいろとあります。運動不足や生活習慣病、難聴などが影響を及ぼしているのですが、そういった中で修正が可能なものとしては、糖尿病、大気汚染、飲酒の三つの影響が特に大きいという研究結果が英オックスフォード大学から報告されています。
この3つは、以前から認知症リスクとなっていましたが、これが特に脳内の弱い神経ネットワークに影響して、何らかの変性を起こしてしまうようです。
また、このリスクは心臓の血管や統合失調症、アルツハイマー病、パーキンソン病などにも関連しているようです。
直接の原因となる脳の萎縮や血管の詰まり、代謝変化などは日頃の心がけである程度予防できるように感じます。
少しずつの積み重ねが後々つながってくるので、頑張りたいところですね。
2024年2月25日 08:50
肥満遺伝子?
 親が患っている病気などが、子供にも遺伝する可能性はあります。
親が患っている病気などが、子供にも遺伝する可能性はあります。腰痛でも、約3割が子供に遺伝するともいわれ、ヘルニアや脊柱管狭窄症では発症する遺伝確率は50%もあるそうです。
また、肥満も遺伝する可能性が高く、一緒に生活していると生活習慣などが似ているので、食生活や運動習慣が同じようになっているとも考えられています。
他にも遺伝子は、体重を増えやすくする状態にも影響し、わずかに太りやすくするような遺伝子の変異は何百個もあるといわれています。
このような遺伝子の変異を複数受け継いでいる人が肥満につながりやすい生活を送っていると、肥満のリスクは大きくなります。
ある研究データによると、脳の視床下部は空腹感と代謝を調節しますが、こういった部分にうまく働かなくなる遺伝子を持っている人は、そうでない人に比べて体重が約5kg少なく、肥満になるリスクは半分だったといわれています。
人それぞれ特徴がありますので、病気であれば未然に防げるように気をつけながら、ダイエットも自分に合ったものを選択するのが健康的だと思います。
2024年2月14日 08:57
<<前のページへ|1|2|3|4|5|6|7|8|次のページへ>>
« 対処療法 | メインページ | アーカイブ | 原因不明の痛みや症状 »