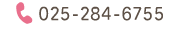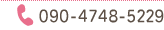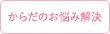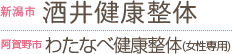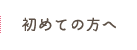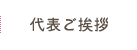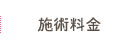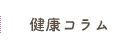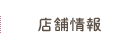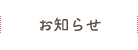カテゴリ
月別 アーカイブ
- 2025年5月 (1)
- 2024年8月 (2)
- 2024年7月 (4)
- 2024年6月 (3)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (3)
- 2023年9月 (2)
- 2023年8月 (7)
- 2023年2月 (1)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (2)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (3)
- 2022年5月 (2)
- 2022年4月 (1)
- 2022年2月 (1)
- 2021年12月 (1)
- 2021年10月 (2)
- 2021年7月 (1)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (2)
- 2021年1月 (1)
- 2020年12月 (3)
- 2020年11月 (3)
- 2020年10月 (7)
- 2020年9月 (1)
- 2020年5月 (5)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (6)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (2)
- 2019年12月 (4)
- 2019年11月 (4)
- 2019年10月 (4)
- 2019年8月 (1)
- 2019年5月 (1)
- 2019年4月 (1)
- 2018年8月 (1)
- 2018年4月 (2)
- 2018年3月 (2)
- 2018年2月 (1)
- 2018年1月 (3)
- 2017年12月 (9)
- 2017年11月 (12)
- 2017年10月 (10)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (2)
- 2017年7月 (16)
- 2017年6月 (1)
- 2015年10月 (5)
最近のエントリー
健康コラム 運動
高齢者の不眠症に大効果!
高齢者の不眠症に大効果!
筋力強化運動が最も効果的と判明…新たな研究結果

タイのマヒドン大学のキティポン・ナガビロジ教授らの研究チームは、不眠症を抱える高齢者約2000人を対象とした24件の臨床試験をメタ分析した。
その結果、筋力強化運動が睡眠の質の改善に最も効果的であることが判明した。
この研究結果は、医学誌「家庭医学と地域社会保健(Family Medicine and Community Health)」に5日付で発表された。
研究チームによると、「高齢者の5人に1人が不眠症を抱えており、睡眠の質の低下はさまざまな健康問題や認知機能の低下と関連している」という。
さらに「これまでの研究では、運動が不眠症の緩和に役立つことが示されているが、どのタイプの運動が最も効果的であるかははっきりしていなかった」と指摘した。
そこで、不眠症と診断された60歳以上の2045人を対象に、運動の種類ごとの効果を比較する24件の国際的な臨床試験データを分析した。
臨床試験では、運動の種類ごとの効果を比較するため、以下の運動が実施された。
サイクリング、水泳、速歩、ガーデニングといった「有酸素運動」、ウェイトトレーニングや腕立て伏せなどの「筋力強化運動」、ステップアップやつま先立ち歩行といった「バランス運動」、体操やヨガなどの「柔軟性運動」、さらに複数の運動を組み合わせた「複合運動」だ。
運動の効果はグローバル・ピッツバーグ睡眠質指数(GPSQI)を用いて評価。
その結果、筋力強化運動の改善効果が5.75点と最も高い数値を示した。
他の運動と比較すると、有酸素運動は3.76点、複合運動は2.54点の改善効果に留まった。
非運動療法の中では「睡眠教育」が最も効果的だったが、筋力強化運動には及ばなかったという。
研究チームは「筋力強化運動と有酸素運動は、日常的な活動と比べて臨床的に有意なレベルで睡眠の質を向上させる」とし、「高齢者は身体機能の制約により一部の運動が難しい場合もあるが、それでも筋力強化運動が高齢期の不眠症解消に最も効果的な運動である」と結論付けた。
MSNより転載
2025年5月 6日 13:04
認知症
 認知症になるリスク因子は、いろいろとあります。
認知症になるリスク因子は、いろいろとあります。運動不足や生活習慣病、難聴などが影響を及ぼしているのですが、そういった中で修正が可能なものとしては、糖尿病、大気汚染、飲酒の三つの影響が特に大きいという研究結果が英オックスフォード大学から報告されています。
この3つは、以前から認知症リスクとなっていましたが、これが特に脳内の弱い神経ネットワークに影響して、何らかの変性を起こしてしまうようです。
また、このリスクは心臓の血管や統合失調症、アルツハイマー病、パーキンソン病などにも関連しているようです。
直接の原因となる脳の萎縮や血管の詰まり、代謝変化などは日頃の心がけである程度予防できるように感じます。
少しずつの積み重ねが後々つながってくるので、頑張りたいところですね。
2024年2月25日 08:50
運動で癌予防
 アメリカのデータですが、男性は1年当たり1万4,277人、女性は同3万2,089人が、運動不足により癌を発症していると推計されています。
アメリカのデータですが、男性は1年当たり1万4,277人、女性は同3万2,089人が、運動不足により癌を発症していると推計されています。男性よりも女性において、運動不足の影響が大きく現れている可能性があるようです。
癌の部位別に見ると、胃癌の発症が多く、次に子宮内膜癌、腎臓癌、大腸癌、食道癌となっています。
しかし、山岳地帯にある州(特に北部あたり)は、運動不足の影響が少なかったのです。
寒くなりやすい地域や運動が行い難い場所では、その地域に住んでいる人の生活が運動が行いにくい状態でも、それなりに代謝が良いのかもしれません。
運動不足だけが影響するわけでは無く、ストレスなども関係します。
それでも、適度な運動で代謝アップやストレス発散に繋がれば、健康的になれるのではないでしょうか。
2023年2月 8日 17:10
速歩きは健康にいい?
 DNAの研究で「速歩きの人は老化が遅い」と判明
DNAの研究で「速歩きの人は老化が遅い」と判明
イギリス人40万人以上の遺伝子データと歩行ペースを分析した大規模な研究により、運動量に関係なく「歩くのが速い人は老化が遅い」ということが示されました。
これにより、歩くのが速い人とそうでない人では、中年期にさしかかるころの老化の度合いに16歳分もの差が発生することが分かりました。
これまでの研究により「歩く速度によって心疾患で死亡するリスクが変化する」ことや、「歩く速さと脳や体の老化には関係がある」ことなどが知られていますが、因果関係までは証明されていなかったので、単に健康な人ほど速く歩けるだけの可能性が捨てきれないという課題がありました。
この問題について、イギリス・レスター大学の運動学者であるトム・イェーツ氏は、「私たち研究者は、歩行ペースが健康状態を示す非常に強い予測因子であることを明らかにしてきましたが、実際に『速歩きをすると健康になれる』ということを確認するには至っていませんでした」と話しています。
歩く速さと老化の関係を解き明かすカギとして、イェーツ氏らの研究チームが注目したのがテロメアです。
細胞内の染色体の末端にあるテロメアは、靴ひもの先端の固い部分のように遺伝子を保護する役割を果たしています。
しかし、テロメアは遺伝子が複製される度に少しずつ短くなるので、最終的にはテロメアが短くなりすぎて細胞分裂ができなくなります。
これは「複製老化」と呼ばれており、遺伝子が損傷した細胞が無軌道に増えてがん化するのを防ぐ一方で、人体のさまざまな老化現象の原因もなっていると考えられています。
テロメアと健康の複雑な関係は完全には解明されていませんが、研究チームはテロメアの長さが老化の度合いを調べるのに最適な指標になると考えて、UKバイオバンクの登録者40万5981人の遺伝子データと自己申告による歩行速度、そして参加者が装着したウェアラブルデバイスによる活動追跡記録のデータを分析する研究を行いました。
その結果、歩くのが速い人は白血球から得られたテロメアの長さである白血球テロメア長(Leukocyte telomere length:LTL)が有意に長いことが判明しました。
その一方で、逆にLTLが長ければ歩くのも速いということはなかったため、これにより歩く速さとLTLの間の因果関係も確かめられました。
論文の筆頭著者であるパディー・デンプシー氏は、研究結果について「遺伝子データを用いることで、歩く速さとテロメアの長さの因果関係を強力に証明することができました。
また、ウェアラブルデバイスからのデータでも、速歩きを始めとする習慣的な活動の強度が果たす役割は大きいことが裏付けられています」と評価しました。
さらに同氏は、「この結果は、歩く速さの測定で簡単に慢性疾患や老年症候群のリスクを調べることが可能であり、どのような生活改善をするかの介入を考える上でも歩行の速度が重要な役割を果たすことを示唆しています。
例えば、ただ歩行量を増やすだけではなく、バス停までいつもより速く歩くことを目標にするといったことが可能なのです。
ただし、これを確認するにはさらなる調査が要ります」と述べて、速く歩くのを心がけることが老化対策のポイントになるとの見方を示しました。
2022年5月22日 23:42
骨を強くするには、骨への刺激も大切
 気候が良くなると外出する機会が増えます。
気候が良くなると外出する機会が増えます。最近は、新型コロナウイルスの影響で室内で過ごす時間が増え、運動量の低下も気になるところです。
運動は気分転換にもなりますし、筋肉量の維持もできます。
また、骨に刺激を与えることで骨を強くもします。
そして日光にあたることで、カルシウムの吸収を助ける役割のあるビタミンDも作ることができます。
重力が無い宇宙空間では骨への刺激が少ないため、骨の形成よりも吸収が上まわった状態が続き、通常の10倍以上の速さで骨量が減っていきます。
これは、骨粗鬆症(こつそしょうしょう)と同じ状態だとも言われ、加齢で骨の吸収と形成のバランスが崩れているのと似ています。
また、体内にあるカルシウムの99%を蓄えているのが骨です。
残りの1%は血中に存在して、これが筋肉の収縮や情報伝達などに使われます。
もし血中のカルシウムが不足すると、破骨細胞の働きで骨を溶かして補います。
その後は、骨芽細胞によって骨は修復されるのが通常ですが、何かしら問題があると、修復が間に合わなくなって骨が弱くなってしまうこともあります。
そうなる前に、カルシウムの適度な摂取と、運動は日頃から大切ですね。
2022年4月19日 14:35
楽しめる運動を
 健康で注目されるのが、運動や食事の見直しです。
健康で注目されるのが、運動や食事の見直しです。どちらも、意識を変えるだけで健康に大きく影響します。
特に運動は、続ける事で寿命が伸びるとも言われ、運動の内容はなんでも良いという研究の報告もあります。
運動の良い部分は、体を動かし適度な筋肉を維持し続けるところにあります。
さらに、「楽しい」といった部分で、友人や同じチームの仲間に会えるといった点も、精神的なリラックスも、体の余計な緊張をほぐしているのもあります。
運動は、量よりも楽しめて行えるものが、自分にとって一番合うのかもしれません。
新潟市、阿賀野市の治療系整体なら、酒井健康整体、わたなべ健康整体へ。
2020年10月25日 22:43
ウォーキングやジョギングが身体に与える影響
 ウォーキングやジョギングによって脳に物理的な軽い衝撃が繰り返されることで、脳の働きが改善する可能性が報告された論文があります。
ウォーキングやジョギングによって脳に物理的な軽い衝撃が繰り返されることで、脳の働きが改善する可能性が報告された論文があります。適度な運動には、身体疾患はもちろんアルツハイマー病やうつ状態などの精神疾患の予防にも有効とのことです。
著者らは、運動による頭部にかかる適度な衝撃が関与していると結果をまとめています。
運動がなぜ精神面に好影響を及ぼすのかはよく分かっていないとなっていますが、考えられる1つに、歩く際の衝撃の一つに「かかと」からの刺激があります。
この刺激は、骨を伝わって首や頭へ流れ 頭に近づくにつれて刺激量が小さくなっていきます。
例えば、脊椎などに歪みがあってそれの影響で 正常に刺激が抜けなくなったり、刺激が小さくならないなどの問題が出ると 腰痛を悪化させたり、膝や首を痛めると行ったことに繋がります。
こうなってしまうと、頭への適度な刺激が無くなったり、また強すぎて反対に悪くなってしまうこともあります。
これも踏まえ、運動と身体の状態も診ていく必要があります。
新潟市,阿賀野市の整体なら酒井健康整体、わたなべ健康整体へ!
2020年4月19日 11:09
運動などで汗をかくのをお勧めします。
 マラソンのように長距離を走れるのは、動物では人間だけです。
マラソンのように長距離を走れるのは、動物では人間だけです。チーターのように120kmで走れて、更に5秒で時速100km!でも、長距離は走れません。
それは、毛深い動物には汗腺が少ないためで、また、犬や馬などは、毛が短く緻密で汗腺も多くあるので、瞬発的には速く走れます。
それに加えて、速く走れる動物は、ハァハァと口でも体温を調節できます。
これは、人間でも走ると行われますが、喉のあたりにある動脈を冷やして体温を調節する働きがあります。
しかし、もっと体温を冷却できる方法が人間には備わっています。
それが「頭からの発汗」です。
これによって、より速く脳を冷却する事ができるのです。
更年期障害などで頭に汗をかきやすくなる場合がありますが、ホルモンのバランス障害だけでなく、脳にも熱がこもっている可能性が十分にあります。
つまり、頭をよく使っている状態で、様々なものに反応してしまいます。
だからこそ、ストレスを感じやすいのかもしれません。
もし、ストレスを感じやすいと感じているのならば、運動などで汗をかくのをお勧めします。
それによって脳の熱を下げる事ができ、冷静になれます。
新潟市,阿賀野市の整体なら酒井健康整体、わたなべ健康整体へ!
2020年2月 4日 23:19
「座りっぱなし」が喫煙と同じぐらい身体に悪い理由
 「座りっぱなし」が「喫煙」と同じぐらい身体に様々な悪影響を与えることはご存知でしょうか?
「座りっぱなし」が「喫煙」と同じぐらい身体に様々な悪影響を与えることはご存知でしょうか?座りっぱなしで寿命が短くなる。
座りっぱなしで糖尿病(2型)になる確率が高くなる。
座りっぱなしで心疾患にかかる確率が64%高くなる。
座りっぱなしでがん(前立がんや乳がん)リスクが高くなる。
さらに座りっぱなしは、腰痛や運動不足を引き起こします。
■座りっぱなしが良くない理由
なぜ座りっぱなしは良くないのでしょうか?
座った状態は、身体をほとんど動かしていない状態=筋収縮をほとんどしていない状態です。
一方、身体の血流は筋肉を収縮することでより循環します。
特にふくらはぎの筋肉収縮は足にある血流を心臓に戻すのに重要な役割を果たしていますが、座っているとふくはらぎの筋肉はほとんど使われません。
また、腰の筋肉が血流不全になり、それが腰痛を引き起こします。
座っていると腰が痛いという人は多いのではないでしょうか?
座りっぱなしが原因のひとつかもしれません。
ちなみに“世界で一番座っている時間が長い”のは、日本人だと言われています。
健康のためにも、たまには歩きながら会議や考え事をしてみてはいかがでしょうか?
またそれが難しい場合、30分に一回は休憩がてら立ち上がり簡単なストレッチをしましょう。
それだけでも健康な生活に近づくはずです。
最近は「スタンディングデスク」といって立ったままデスクワークができるような机も多く発売されています。
このような形で工夫するのもよいかもしれませんし、会議などを歩きながら行うのも効果的です。
座りっぱなしを防いで健康な生活を手に入れましょう。
新潟市,阿賀野市の整体なら酒井健康整体、わたなべ健康整体へ!
2019年5月 7日 22:46
明日の試合に間に合いますか?
診ると、その小学生の男の子の脚はスポーツ障害の一つであるシンスプリント(すねの下側に痛みが発生する症状)でして、十分な筋力が整っていないうちから激しい運動をした際に起こりやすく、走るスポーツに特に多いという症状でした。
本人も辛そうです。
その子の母親に「無理です。」とお伝えしましたが、痛みは軽減できると思いますということで治療を始めました。
治療の結果、痛みは0(ゼロ)ではありませんが、大分軽減できました。
しかし、治ったわけではありません。
その子の母親に「試合に出れますか?」と聞かれたので休む事をお勧めしたのですが、納得してくれなかったようで、不機嫌そうな顔でした。
小学生でどのくらい大事な試合なのかが分かりませんが、「この子の身体とその試合どっちが大切ですか?」と問いたかったです。
しかし、男の子が一番辛いわけで、本人は休みたいようでしたが、母親の方が...。
2回目に来られる事はなかったのでその後どうなったか分かりませんが、恐らくおかしなことになっていることでしょう。
親が夢中になるのは構いませんが、健康であってのスポーツです。
身体が悲鳴上げてもやるのが美徳という時代ではありません。
根性だけでは身体を壊します。
 身体に異常があるということは、練習内容やフォームなどが間違っているケースも多々あります。
身体に異常があるということは、練習内容やフォームなどが間違っているケースも多々あります。それを無視してやった為に、将来にわたって障害が残る方もおります。
それに、痛い思いしながら練習した所で上達するわけないですし、試合で良い結果を出すのも難しいです。
痛い思いをしながらの練習は、かばうために変な癖がつくことが多く、治った際にその癖を抜くのが大変な事もあります。
身体に異常がありましたら無理せずにさっさと治して、万全な状態で望んだ方が断然早く成績が上がります。
また、普段からメンテナンスなど含め、練習内容が合っているのかを確かめながら行うのも大事です。
どんなに一生懸命練習しようが、あってなければ無駄なだけです。
新潟市,阿賀野市の治療系整体 酒井健康整体、わたなべ健康整体
2018年2月17日 16:50